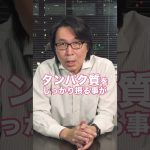「手足がいつも冷たい」「布団に入っても体が温まらない」
そんな“冷え”に悩まされている女性はとても多いですよね。
でも、その冷え、もしかすると“ホルモンバランスの乱れ”が関係しているかもしれません。
冷え性と聞くと「血行が悪いから」と思われがちですが、実は女性特有のホルモンと深くつながっているのです。
本記事では、ホルモンバランスと冷え性の関係、そして女性が意識したい“あたためケア”について、やさしく丁寧にご紹介していきます。
毎日をもっと軽やかに、心も体もあたたかく。
そんな自分を目指してみませんか?
1. 冷え性とは?女性に多い理由とは?
◆ 冷え性の定義とは?
冷え性とは、自覚的に「寒さを感じやすい」「体が温まりにくい」と感じる状態のこと。特に、手足の先や下半身の冷えを強く感じる方が多いのが特徴です。
体温そのものが低いわけではなく、末端の血流が滞っていたり、自律神経が乱れていたりすることが原因となっているケースがほとんどです。
◆ なぜ女性に多いの?
- 筋肉量が少なく、熱を生み出しにくい
- 月経・妊娠・出産などホルモンの影響を受けやすい
- ストレスに敏感で、自律神経が乱れやすい
こうした体のしくみから、女性は男性よりも冷えを感じやすい体質と言えるのです。
2. ホルモンバランスと冷え性の深い関係
◆ ホルモンバランスって何?
ホルモンとは、体内のさまざまな機能を調整してくれる“メッセンジャー”のような存在。
中でも女性は、**エストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)**という2つのホルモンが、月経周期に合わせて絶えず変化しています。
◆ ホルモンが冷えにどう関係するの?
① エストロゲンの低下 → 血行不良に
エストロゲンは、血管をしなやかに保ち、血流をスムーズにする働きがあります。
加齢やストレス、生活習慣の乱れでエストロゲンが減少すると、血流が滞りやすくなり、冷えを感じやすくなるのです。
② プロゲステロンの作用 → 水分を溜めこみやすくなる
プロゲステロンが増える生理前は、体が水分をため込みやすくなる時期。これがむくみや代謝の低下を招き、冷えやすい体質へと傾きやすくなります。
③ 自律神経の乱れ → 体温調整がうまくいかない
ホルモンの変動は自律神経にも影響を与えます。
自律神経が乱れると、手足への血流がうまく届かず、体温のコントロールがうまくできない状態になってしまいます。
3. ホルモンを整えて“冷えにくい体”を育てる方法
◆ ① 食生活で体の内側からサポート
◎ 大豆製品(納豆・豆腐・豆乳)
植物性エストロゲンである「イソフラボン」が、女性ホルモンのバランスをサポート。ホルモンのゆらぎによる冷えをやさしくケアします。
◎ 鉄分&ビタミンB群
女性は鉄分不足になりやすく、貧血による冷えにも要注意。
レバー、赤身肉、あさり、卵、玄米、ほうれん草などを意識的に摂りましょう。
◎ 体を温める食材
しょうが、にんにく、ねぎ、かぼちゃ、味噌汁などを日々の食事に。内臓を温めることで、全身の巡りがスムーズに。
◆ ② ストレスケアで自律神経を整える
- 夜はスマホを手放し、あたたかいハーブティーやアロマでリラックス
- 深呼吸や軽いストレッチを習慣に
- 「頑張りすぎない」日をつくる
ストレスは、ホルモンと自律神経の大敵。心のゆとりが、冷え対策の土台になります。
◆ ③ 睡眠をしっかりとる
眠っている間に、ホルモンや自律神経はバランスを整えてくれます。
寝る1〜2時間前にはスマホやテレビを控え、ぬるめのお風呂で体を温めてから就寝するのがおすすめです。
4. 冷え対策のためのセルフケア習慣
◎ 朝の白湯を習慣に
体の中からじんわり温め、内臓の冷え対策&代謝アップにも効果的です。
◎ 冷やさないファッションを
お腹・足首・首元を冷やさないことがポイント。冷えとり靴下や腹巻きもおすすめです。
◎ ゆっくり入浴タイム
ぬるめのお湯(38〜40℃)に15分〜20分浸かることで、副交感神経が優位になり、リラックス&血行促進。
5. まとめ|ホルモンと向き合って、あたたかな私へ
冷え性は、ただの「体質」や「体温の問題」ではありません。
ホルモンという女性の体にとって繊細なリズムが、冷えと深く関わっているのです。
無理に変えようとせず、やさしく整えていくこと。
今日の食事にひと工夫、寝る前の時間にひと呼吸、そんな“ちいさなあたため”の積み重ねが、心も体もぽかぽかとしたやさしさを運んでくれます。
「冷えは、心からのSOSかもしれない」
そう思ったときは、ちょっと立ち止まって、自分の体と向き合ってみてくださいね。




![【皮膚科医実践】美肌のための5つの習慣 / Five Habits for Beautiful Skin [Practicing Dermatologists]](https://beautiful-skin-care.tokyo/wp-content/uploads/2020/07/9a34b5c008b76927c06f96829dad0352-150x150.jpg)